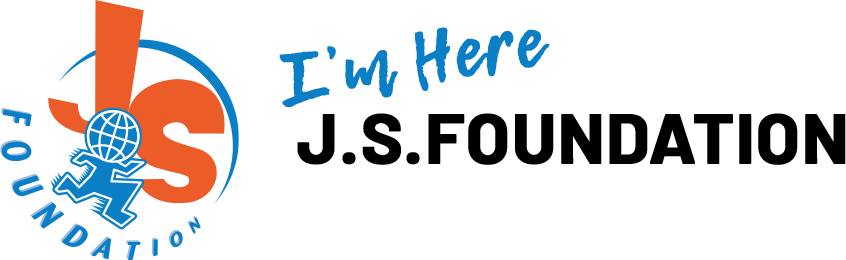- 2001.06.05 UP
-
5月の始め、なんとか時間をやりくりし、思い出の地、ネパ-ルを訪問する事ができました。
5年ぶりのネパ-ルの山々への再会は、こころ洗われる思いでした。
ネパ-ルへ行ったのは、もちろん私達がサポートしている子供病院を訪ねるために…5月8日と10日、前回の活動報告の中で説明した、「ネパ-ルで、健康保険の様なシステムをつくりたい」というプロジェクトに携わるAMDAの岸田さんに同行し、無医村へのフィールドワークに参加しました。
日本で一番良い季節の所からやってきた私は、連日35度から37度という高温多湿の気候に、この後の数日間、体力を奪われ続けることとなりました。
インドとネパ-ルの国境に広がるタライ平野には、小さな村々が点在しています。
ほとんどの村には医者がいないため、私達にとっては日常的な医療行為を受けるといった事は、彼等には特別な事のようです。
病院に行く時には特別な服を着て、ある者は乗り合いバスで、ある者は徒歩で何時間も何日もかけ、大きな町までやってくるのです。
そんな村々へこちらから赴き、無料で医療・健康衛生教育を行うこと、そして子供達に文字の読み書きを教えること、これがJ.S.基金がサポートしているプロジェクトです。
子供達に、読み書きを教える青空教室に参加した私は、子供達の吸収力に驚かされました。
まるで乾いた砂に水がしみ込むように、先生の言葉を吸収していくのが手に取るように分かりました。
先生が黒板に文字を書くと、子供達は一生懸命にそれをノートに写すのです。
「子供達には、まだ、文字という感覚が無いのです。彼等彼女等には、絵を写生しているのと同じなのです。」
現地スタッフの言葉は、目の前で教育を楽しんでいる子供達のキラキラした目と共に、記憶の中に強烈に残っています。
この国では、まだまだ子供という労働力を必要としているとのこと。
そのために、ほとんどの子供達は、学校に行くことが出来ないそうです。だからなのでしょう。
この青空学校や医療・健康衛生教育も、彼等にとっては、娯楽映画を見るのと同じぐらい楽しみなものとなっているようです。
少なくとも、私にはそう写りました。
電気も通っていない村々へ、黒板とチョーク、ノートと鉛筆、医療・健康衛生教育の為のビデオ機材一式を持って飛び回っているボランティアのスタッフを、少しうらやましく思いました。
今現在、彼等は8つの村を巡回しているそうです。
これからも、少しづつ、このプロジェクトの輪を広げていってくれることでしょう。
J.S.基金は、このプロジェクトの立ち上がりから携わってきましたが、別れ際、5年間継続してサポートして行くことを、堅く約束してきました。
皆様の善意は、ここではこうした形で活かされていることに、とても誇りに感じています。


5月9日、11日、12日の3日間、子供病院を訪ねました。病院は今、新しい病棟の建設が行われていました。
規模が大きくなれば、援助も大きなものを必要としてくるでしょう。
ベッドが足りずに廊下で寝ている患者を見ると、まだまだ足りないものがあるようです。
短い訪問中にも、いろいろな事がありました。
一番衝撃的だったのは、瀕死で生まれた赤ちゃんへの、緊急蘇生医療の一部始終でした。
日本人の私には信じられない事でしたが、子供の父親が、看護婦と交代でアンビューという手動の器具を使い、子供の口に空気を送っていたのです。
手動の人工呼吸器と言ったところでしょうか。
「医療行為は、全て医者任せ」が当然の事と捕らえていた私はとても驚かされましたが、と同時に、ここでは生と死がとても身近なものなのだと痛感させられた出来事でもありました。
残念ながら、その子供は4時間の短い命を、父親の手の中で終わらせてしまいましたが、父親が純粋に子供を助けようとする行為は、とても美しく私の記憶に残っています。高温多湿の気候に奪われた体力も、現地で受けた喜びで補い、爽やかな気分で帰路につくことができました。

ヒマラヤの山は美しく、夕暮れ時に赤くその身を染めていました。
確かにあの山には神が住んでいるのだと、疑う余地も無い程、人々は神と一体化して生活を送っていました。J.S.Foundation.代表 佐藤佐江子